私たちが学生時代に一度は耳にしたことのある「スクールカースト」。教室という閉じられた空間の中で、無意識のうちに序列が生まれ、ある人は中心に、ある人は周縁に位置づけられていく。このような現象は、なぜ起こるのでしょうか?そして、その序列の中で「上に行くこと」にどれほどの意味があるのでしょうか?
本稿では、社会心理学や教育社会学の知見を踏まえながら、スクールカーストの背景を解き明かし、最終的に「本当に大切なこと」に迫っていきます。
スクールカーストの正体:「見えない秩序」の構造
「スクールカースト」という言葉は、インドの伝統的な身分制度「カースト」に由来しています。日本では、2000年代後半から若者文化の文脈で用いられるようになり、「教室内での非公式な身分階層」として定義されています。
教育社会学者の本田由紀氏は、現代の学校において「公式の評価」とは別に、「生徒同士による評価」が大きな意味を持つことを指摘しています。スクールカーストはまさにこの「非公式の評価体系」によって形成されます。
その序列は、主に以下の要因によって決定されます:
- 外見(顔立ち、スタイル、服装センス)
- コミュニケーション能力(ユーモア、発言力、対人スキル)
- スポーツ能力や人気度
- SNSなどを含む情報発信力
これらは、学力や努力といった「公式な尺度」とは無関係であるため、制度的な裏付けがないにも関わらず、強固な影響力を持つのです。
「閉じられた環境」が序列を強化する
社会心理学の観点から見ると、スクールカーストが生まれる背景には、「集団内ヒエラルキー形成」の本能的傾向が関係しています。人間は集団内で自らの立ち位置を把握しようとする傾向があり、これは狩猟採集時代からの社会的進化の結果とされています(Henrich, 2016)。
特に学校という空間は、生徒同士の交流が限定的で、かつ同質的な集団で構成されるため、「他者との比較」が避けられません。そこにSNSが加わることで、常に「誰が中心か」「誰が注目されているか」という情報が可視化され、序列はより固定化されていきます。
スクールカーストを「勝ち上がる」意味はあるのか?
多くの若者が、「スクールカースト上位=人生の勝者」という錯覚に陥ります。しかし、これは極めて限定的な価値観に過ぎません。
実際、学術的な研究でも、カースト上位の生徒が自己肯定感や幸福度において必ずしも高いわけではないことが示されています(矢野・2020)。また、スクールカースト上位であっても、それが社会に出た途端に無効化されることは多くの人が体感的に知っているはずです。
一方で、周縁にいた人々が、大学、職場、あるいは創作や研究の場で、自らの価値を発揮するケースは珍しくありません。なぜなら、社会はより多様で、複雑で、異質な個性を必要としているからです。
本当に大切なこと──序列よりも「自分の軸」
スクールカーストが生み出す最大の問題は、「自分の価値を他者との比較でしか見いだせなくなる」ことです。これは自己効力感の低下や、無力感、さらには長期的な精神的苦痛につながることがあります。
重要なのは、「どの位置にいるか」ではなく、「自分が何を大事にしたいのか」という価値観の軸を持つことです。現実には、スクールカーストが全く関係しない場面――文学、音楽、数学、科学、職人技、起業、対人支援など――が無数に存在します。
むしろスクールカーストに過度に囚われないことで、自分だけの才能を発見し、磨き上げる自由が生まれます。
おわりに
スクールカーストは、人間の社会的本能や環境によって生じる現象です。しかしそれは、あくまでも一時的かつ限定的な秩序であり、人生の価値を決定づけるものではありません。
本当に大切なのは、自分の中に軸を持ち、自分にしかない価値を信じること。どんな位置にいようと、あなたの人生は、あなたが形づくるものです。


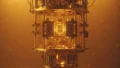

コメント