2025年5月20日、ノルウェーの首都オスロで開かれた「アーベル賞」の授賞式にて、京都大学数理解析研究所の柏原正樹特任教授(78)が、栄えある賞を受賞した。ノルウェー国王ハラルド5世から直接ガラス製の盾を受け取った柏原氏は、満員の会場から長い拍手で祝福された。
アーベル賞とは、数学の世界で最も権威ある賞のひとつで、「数学界のノーベル賞」とも称される。2003年に創設されて以来、世界中のトップ数学者に授与されてきたが、日本人の受賞は今回が初めてだ。賞金は750万ノルウェークローネ(日本円で約1億円超)にのぼる。
柏原氏の受賞理由は、「代数解析学および表現論、特にD加群理論の発展と結晶グラフの発見に対する根本的な貢献」。しかし、専門外の人々にとっては、「それが何の役に立つのか」「何がそんなにすごいのか」が分かりにくいかもしれない。
では、これを日常のたとえ話で説明してみよう。
数学の“地図”を描くということ
私たちの暮らしは「数式」とは無縁に見えるかもしれないが、実はコンピュータ、医療、物流、AI、通信、金融など、あらゆる分野の根幹には高度な数学がある。その中でも、柏原教授が開いた「D加群理論」と「結晶グラフ」は、まるで未開の森の中に道を切り拓き、見えなかった地図を描き出すような発見だった。
たとえば、数学の世界を「広大な森」にたとえてみよう。この森には無数の木(分野)があり、木と木の間には道がなかった。従来の研究では、一本の木をひたすら登るような研究が多かった。ところが柏原教授は、異なる木と木をつなぐ“橋”や“道”を発見し、全体を見渡す新しい視点を数学界にもたらした。
特に「D加群(ディーかぐん)」という道具は、難解な関数や微分方程式を“代数”という別の言葉で言い換える翻訳機のようなものであり、物理現象や複雑な構造を理解する際に新しい光を当てた。さらに、「結晶グラフ」は、まるで鉱物の中にある見えない秩序を抽出するように、数学の中に潜む対称性を可視化することに成功した。これは量子力学や情報科学にも応用可能な理論であり、まさに未来の技術に影響を与える“基礎科学”である。
恩師の言葉と妻への感謝
授賞式のスピーチで柏原教授は、若き日に受けた恩師・佐藤幹夫氏の教えについて触れた。「数学において新しいものを創造することが大切だと学んだ」と語るその言葉は、まさに柏原氏の研究人生の指針となってきたという。
そして、支えてくれた妻への感謝の言葉も忘れなかった。「私の研究人生を支えてくれたすべての人に感謝します」と語ったその姿には、78歳の数学者としての重みと人間としての温かさが滲んでいた。
日本の数学界にとっての意味
柏原氏の受賞は、日本の数学界にとって大きな意味を持つ。これまでアーベル賞は、欧米の数学者が多く受賞してきたが、今回の快挙は日本の数学研究の深さと広がりが、世界に認められた瞬間でもあった。
ノルウェー・アーベル委員会のホルデン委員長は、「柏原氏は数学の非常に専門的な複数分野をつなげ、新しい景色を見せてくれた」と称賛した。
おわりに
科学の進歩は、日々の暮らしにすぐに現れるわけではない。けれど、私たちが安心して病院にかかり、スマートフォンを使い、AIとともに生きる未来を見据えるとき、必ずそこには目に見えない数学の力が働いている。
その数学の最前線で、新たな地図を描き続けてきた柏原正樹教授。その姿は、科学が単なる知識ではなく、創造であり、人生であるということを、静かに私たちに教えてくれている。

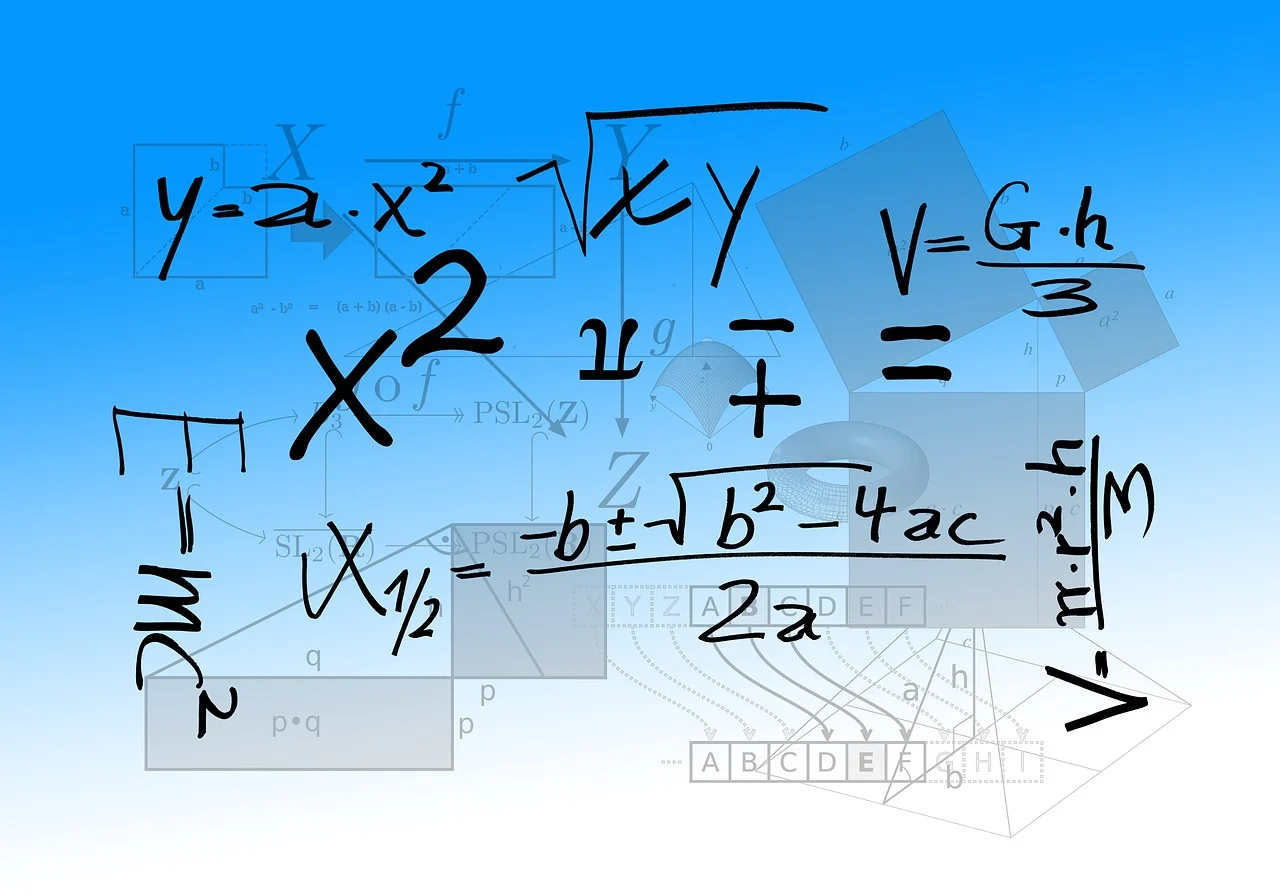
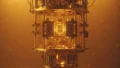

コメント